
Steenzでは、人気コミックを映画化した『夏目アラタの結婚』(2024年9月6日全国ロードショー)の公開を記念して、堤 幸彦監督への座談会インタビューを実施。映画の見どころや制作秘話などについて伺いました。
以前「気になる10代名鑑」に出演し、映画業界で活動していきたい! と意気込む3人が試写に参加し、その後、監督へのインタビューを実施。作品の見どころだけではなく、すでに映画の制作現場で活動している3人からの、リアルな悩みや不安にも耳を傾けてもらいました。これまでドラマ『池袋ウエストゲートパーク』や映画『20世紀少年』をはじめ、数々のヒット作を世に生み出してきた鬼才・堤 幸彦さん。その作品づくりの真髄に迫ります。
原作をある作品を生身の人間に演じさせるプレッシャーと、どう向き合うか
作品をゼロから生み出すこともあれば、原作があるものを映画やドラマにするのも、映画監督の仕事のひとつ。さまざまな作品の映像化を手がけてきた堤さんの原作との向き合い方とは?

林:『夏目アラタの結婚』もそうですが、堤さんがメガホンをとられる作品は、原作があるものが多い印象です。
堤:そうなんですよ。『20世紀少年』『十二人の死にたい子どもたち』など、原作のあるお話ばかりいただくんですよね。
林:原作がある作品を映画化するときって、どんなことを考えているんですか? ものすごいプレッシャーがあると思うんですけど。
堤:何度つくっても、実写化作品をつくるときの苦悩は尽きないですね。実写化するということは、漫画の中で平面に描かれているキャラクターを生身の人間が演じるということ。特にヒットしている作品には、すでにファンのみなさんたちなりの、キャラクター像があるわけです。そうなると、実写のキャラクターに納得ができないファンも当然いるわけで。
林:そうですよね……。
堤:そういったファンたちを、映画で裏切るようなことはしたくない。とにかく原作そっくりにやるのが、僕のやり方。でも、どれだけそっくりできたと思っても賛否両論あって。もちろん、つくるからには覚悟もある。だけど、否定的なメッセージはやっぱり気にしてしまいます。だから今日もあまり否を言わないでね(笑)。
一同:(笑)。
堤:しかし何歳になっても、映画をつくること、特に原作がある作品を扱うことへの難しさや恐怖はずっとありますね。それが、この仕事の面白さでもあるとも思うんですけど。

村田:制作過程においてどこまで原作を意識しているのかは、わたしも気になっていました。
堤:僕はお話をいただいてから、まず、原作を読みます。ありがたいことにヒット作の映画化のお話が多いので、やはりおもしろい作品ばかりなんですよ。でも漫画と違って、映画には”上映時間”という時間的な制約があります。ある特定の時間軸で、ストーリーを切らなければいけないという暴力性を持っているんですよね。
村田:暴力性、ですか。
堤:そう。その暴力性に対して、観る人たちを納得させるためには、映画作品ならではの「解」が必要になってきます。そして、その解に向けて、ストーリーやキャラクターを膨らませることで人を惹きつけることに気を配っています。これは映画ならではこその考え方じゃないかな。原作そっくりにしながらも、映画作品として伝えたいメッセージがないといけないと思っています。
内田:今回の『夏目アラタの結婚』では、キャラクターたちはもちろん、ストーリーの伏線回収やその演出も印象的でした。わたしは原作を読んだことがなかったんですけど、映画を見終わって、原作を読んでみたいなって思いました。

堤:それは嬉しいですね。ぜひ読んでみてください。
いろいろなケースがありますが、映画のストーリーは、脚本家や演出家など、僕を含めてさまざまな人たちと議論しながら作りあげていきます。今回の『夏目アラタの結婚』の原作は、国内外でヒットしているコミックのひとつ。すでにたくさんの人に、ストーリーが受け入れられているわけですから大変でしたよ。
内田:物語が後半にいくにつれて、どんどん真珠の事件の真相が明らかになっていく感じがすごく気持ちよかったです。
堤:脚本も脚本家によってさまざまで、話の運び方が上手い脚本家もいれば、セリフが面白い脚本家もいます。 特に今回は、制作段階では未完結だったこともあって、脚本はかなり難航したんですよ。ちなみに、僕は絶対に脚本を書きません。僕が書いても、あんまり面白くならないんだよね(笑)。
これまでさまざまな作品をつくってきましたが、映画をつくるときは、純粋な魂を持ってしか走りきれなくて。業界に身を置いて何十年も経ちますが、常に初期化して「これがデビュー作だ!」と思わないと、新しいものを生み出すことはできないと思っています。
「何億円払っても、10代の目線は買えない」半径1mの中のいまを記録することの意義
インタビューに参加した3名は、それぞれが映画づくりを学ぶ現役の学生たち。若い世代の作品から刺激を受けることも大いにあると語る堤さんからも、質問が投げかけられました。

堤:普段、僕は学生さんの作品を見ることもあって。皆さんがどんな作品をつくられているのか、気になります。
村田:わたしは映画監督志望で、いまは日本大学芸術学部で映画づくりを学んでいます。ずっと映画が好きで、高校時代からこれまでに監督した作品がいくつかあります。
堤:高校生から! すごいね。
村田:つくっているのは、どちらかというとわたしの日常をベースにしたもので、すごく私的なもの。いまは純度が高いものや理想に向き合おうと思っています。
内田:わたしも似ているかも。つくっているのは自分の記録に基づいたもので、短編が多いです。いつか長編で撮ってみたいという気持ちはありますが、いまは自分の感情をベースにストーリーを描いています。
村田:だから、あまりまだ自分の作風はこうだ! っていうのはわかっていないんですけど……。

堤:人になんて言われるかは関係ないですよ。おふたりの作品へのアプローチは、とても素敵じゃないですか。純粋性ってもしかすると歯がゆくて、鬱陶しいものだと思うこともあるけど、自分の立場なんて、一生歯がゆいし、気持ち悪いもの。
普段のことだから社会に見せるようなことではないって思っているかもしれないけど、そんなことはないですよ。そこにこそ、宝があるはずで。
内田:そう言っていただけて、なんだか少し安心しました。
堤:極論、日常に宇宙人がいたっていいんですよ、自分に見えているなら。そのときにあった事件、それを見ていた自分の純粋性、わたしにはこう見えているんだ! というものを見せてほしいです。10代、20歳の頃に、純粋に撮りたい映画像があるっていうその気持ちも、その世界で見えているものも、どれだけお金を払っても買うことはできません。大人が何億円払ってもね。
だから、自分の半径1メートルの中で起きていることを記録することは、とっても重要。それを積み重ねることで、その人の世界や作風がつくられていくんだと思います。僕だって、”あの夏の日”のことを思い出したいけど、いまはもう、目が霞んで無理なわけで(笑)。
一同:(笑)。
堤:そのときにしかない感情で作品をつくることって、すごく大事なこと。実は、僕もコロナのとき一気に仕事がなくなっちゃって。そのとき、いままでやってこなかったようなところにチャレンジしようと思ってつくった作品があります。『truth~姦しき弔いの果て~』という作品なんですが。
内田:具体的に、どういったところにチャレンジされたんですか?
堤:僕はいま、自分のチームを持っているから、チームを守る必要がある立場にいるのだけど、コロナのときは一気に仕事が止まって、急に不安定になってしまった。でも、だからこそアグレッシブに、いましかつくれないものをつくろうという気持ちで、俳優さんたちと議論してつくりあげたんです。これは予算も少ないインディーズ映画だったんですけど、結果的には、海外のさまざまなところで高い評価をいただくことができました。

林:僕はアクションをテーマに作品をつくっています。両親が映画関係の仕事をしていて、幼いころから現場に行っていたこともあり、自然とその世界に興味を持つようになりました。いまは東放学園に通っているので、堤さんは大先輩です。
堤:まさか、ここで後輩に会えるとはね(笑)。東放学園にはいろんな才能が集まっていますよね。僕は、映画にはあまり触れてこない環境で育って、ひょんなことからこの業界にいるようになって。だから、18歳で東放学園に入っていたら、大学で演劇をやっていたらって思うこともいまだに多いんですよ。そういう意味では、いまの10代、20代の皆さんがつくる作品から刺激を受けることも多くて。あまり年齢で区切る業界でもないけどね。
林:まさに、学園にはすごい人たちがたくさんいます。僕は自分で脚本を書くこともあるんですが、己の未熟さを痛感します。特に、演者の魅力をどう引き出すかっていうのは難しくて。

堤:そこばっかりは経験的なものも大きいよね。でも、不思議なことに僕はいまは、ぱっと見ればこの人がこの役者がどれだけのことができるのか、どんなセリフが適しているのかっていうのを瞬時にわかるんです。主役の役者さん次第で、作品の方向性を決めることもあるんですよ。
林:ええ。
堤:オーディションだって、役者さんはいいものを見せようとしてくるでしょう。力んで、不自然になってしまったり、たどたどしさが出てしまったりする役者さんもいるわけで。でも、作り手としては、例えば、そのたどたどしさを逆に利用して、エンタメ的な要素として引き立てることもできると思うんですよ。監督の腕の見せどころです。それで面白く見えないと僕の負け。監督は役者の個性を活かして、演技ができる環境をつくっていくことが大事だと思います。
かっこよくなくてもいい。他人には譲れない、自分だけの何かを見つけて
最後に、Steenzを読んでいる10代に向けて、こんなメッセージを送ってくれました。

堤:いまはテクノロジーが進歩して、いろんな表現世界がありますよね。率直に羨ましいなって思います。僕らが学生のときって、5分の作品をつくる術がわからなかった。でもいまは、iPhoneひとつで映像が撮れて、編集ができて、さらに発信までできる。iPhoneさえあれば、誰しもが映画監督になれる時代だと思っています。
じゃあ、そんないまの時代に、監督、演出、ディレクターなど映像作品にかかわる人間に求められているのは何か。僕は「抜き差しならない自分」を持っているかどうか、だと思います。いま、映像に関わる人間とは言ったけど、人間には「絶対にこれだけは譲れない」っていう何かが、誰しもにある。立派じゃなくても、かっこよくなくてもいいんですよ。「譲れない何かとは何か?」という問いに向き合ってみてください。何かをずっと調べ倒しているでも、なんでもいいんです。大事なのは、その目線を持っているかどうか。
いつか皆さんの傑作が見れることを、楽しみにしています。
堤 幸彦さんプロフィール

1955年11月3日生まれ、愛知県出身。1995年放送のドラマ「金田一少年の事件簿」で注目を集め、「ケイゾク」「池袋ウエストゲートパーク」や「TRICK」シリーズ、「SPEC」シリーズ、映画「20世紀少年」三部作といった話題作の演出を手がけてきた。映画「明日の記憶」「イニシエーション・ラブ」「天空の蜂」「真田十勇士」「人魚の眠る家」「十二人の死にたい子どもたち」「望み」「ファーストラヴ」「ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”」「truth~姦しき弔いの果て~」、ドラマ「死神さん」「Get Ready!」などの監督・演出作がある。
映画『夏目アラタの結婚』
このプロポーズが、日本中を巻き込む大事件にーー。国内外から高く評価されているベストセラーコミックスが映画化!初めてプロポーズした相手は連続殺人事件の死刑囚だった…死刑囚に結婚を申し込む元ヤンキーに柳楽優弥×日本で最も有名な死刑囚に黒島結菜、『SPEC』シリーズ、『十二人の死にたい子どもたち』の堤幸彦が送る未体験の獄中サスペンス。
2024年9月6日(金)より全国ロードショー。
https://wwws.warnerbros.co.jp/natsume-arata/
出演:柳楽優弥、黒島結菜、中川大志ほか。
監督:堤幸彦
原作:乃木坂太郎「夏目アラタの結婚」(小学館ビッグコミックスペリオール刊)
公式サイト:https://wwws.warnerbros.co.jp/natsume-arata/
配給:ワーナー・ブラザース映画
今回話を聞いた3人
村田夕奈さん
林 隼太朗さん
内田茉侑さん
Photo:Kaori Someya
Text:Ayuka Moriya












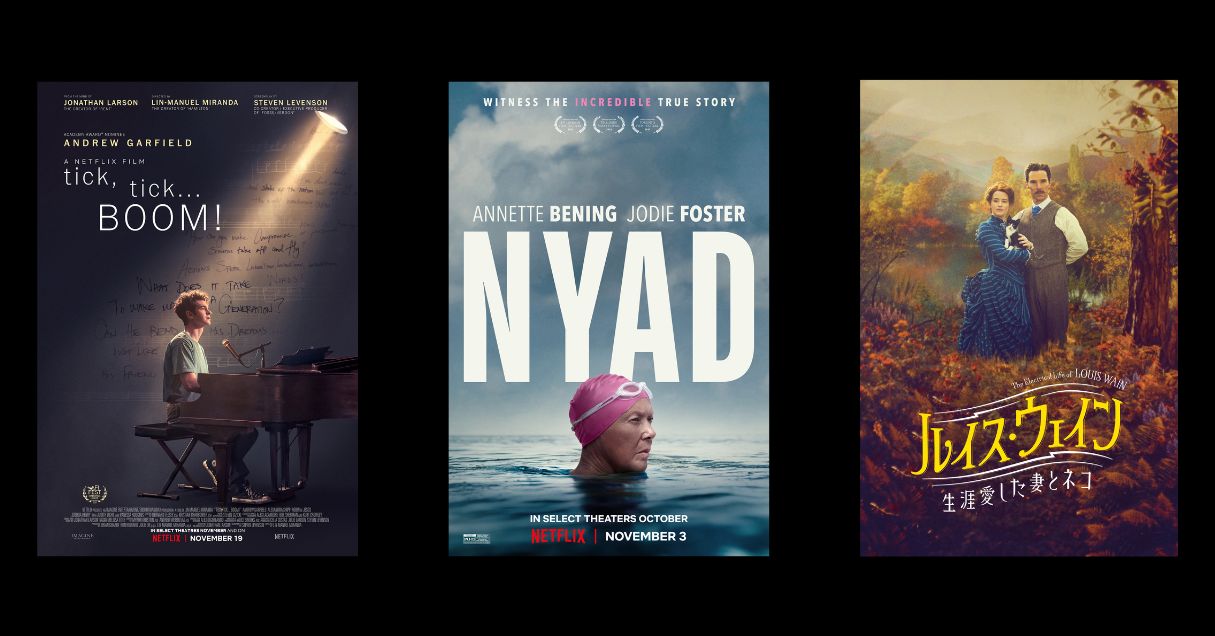

Steenz_Breaking_News.png)
10代のリアル.png)

世の中.png)
特集.png)






