
タイムリーな話題から、カルチャー、さらには社会問題まで、さまざまなテーマについて、リアルな10代の声を聞くシリーズ「10代リアルVOICE」。
今回は「最近読んだ本」について。本離れが進んでいるとされる10代ですが、もちろん読書好きも健在。小説や哲学書から学んだことや心に残ったこと、考え方の変化について、聞いてみました。
1. Souさん「人類の禁忌に触れるテーマから考えさせられた」
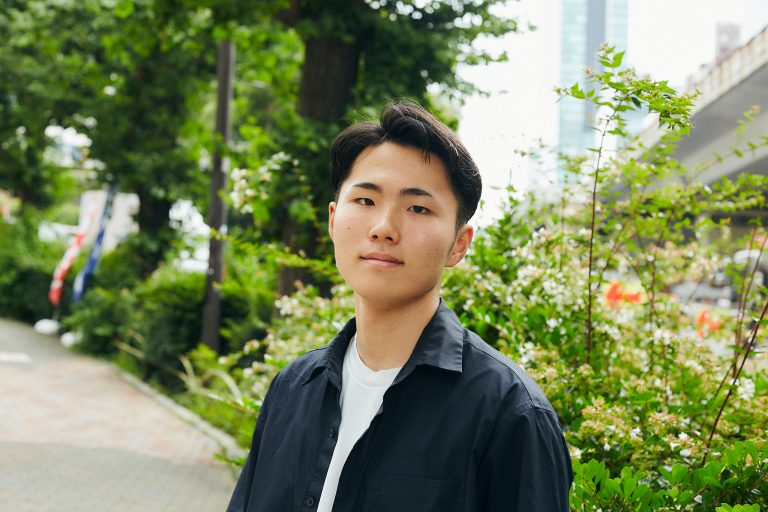
逗子開成高校の部活で、能登半島でのボランティアや珠洲焼の販売企画など新しいボランティアのかたちに挑戦している16歳。
「最近読んだ本で特に印象に残っているのは、松下龍之介さんの『一次元の挿し木』です。第23回『このミステリーがすごい!』大賞の文庫グランプリ受賞した作品なのだそう。
正直、直接的に自分の考え方が変わったという実感はないのですが、クローン人間という“人類の禁忌”に触れたテーマがとても印象的でした。クローンを作ってはいけないのはなぜか、その存在が社会にどんな影響を与えるのかを、少し理解できた気がします」
2. 門口愛実さん「自分を見つめ直すきっかけになった」

発達障がいや不登校に悩む中高生に寄り添う手段として、『インクルーシブ教育』に関心を持ち、SNSでの発信や教育関連イベントの企画を重ね学生団体を立ち上げた17歳。
「文筆家の池田晶子さんのエッセイ集『14歳からの哲学』という本を読んで、とても気に入りました。
自分自身のことを改めて考えるきっかけになり、不思議な感覚に包まれながらページを進めました。哲学的な問いを通して、自分の中に新しい視点が生まれるのが面白い本です」
3. かわかつさん「人が抱える葛藤を知り、寄り添う気持ちを持てた」

慶應義塾大学SFCに通いながら、主権者教育やメディアリテラシー教育に取り組んでいる19歳。
「印象に残っているのは辻村深月さんの小説で、アニメ映画にもなった『かがみの孤城』です。
不登校の子どもたちが抱える心の葛藤や複雑な事情が描かれていて、人それぞれがいろいろな思いを抱えていることに気づかされました。読むことで、相手の立場や状況に寄り添う気持ちが持て、人それぞれ色々なものを抱えているのだと思いました」
安さ重視かデザイン優先か……と服の好みと同じように、本の読み方や感じ方も人それぞれ。これからも「10代リアルVOICE」では、世の中を自分ごととして捉えるティーンの視点を伝えていきます。
Photo:Nanako Araie
Text:Serina Hirano

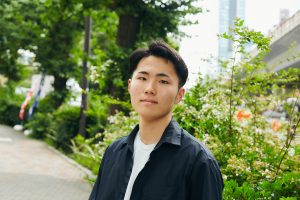










Steenz_Breaking_News.png)
10代のリアル.png)

世の中.png)
特集.png)






