
「気になる10代名鑑」の1015人目は、中田涼介さん(17)。これまで成層圏までスペースバルーンを飛ばすプロジェクト「カイロスプログラム」を主催し、現在は会社を立ち上げAIアプリの開発に取り組んでいる最中です。今後の教育のあり方についてヴィジョンを持つ中田さんに、きっかけとなった自身の通っていた塾での経験や将来の夢について聞いてみました。
中田涼介を知る5つの質問
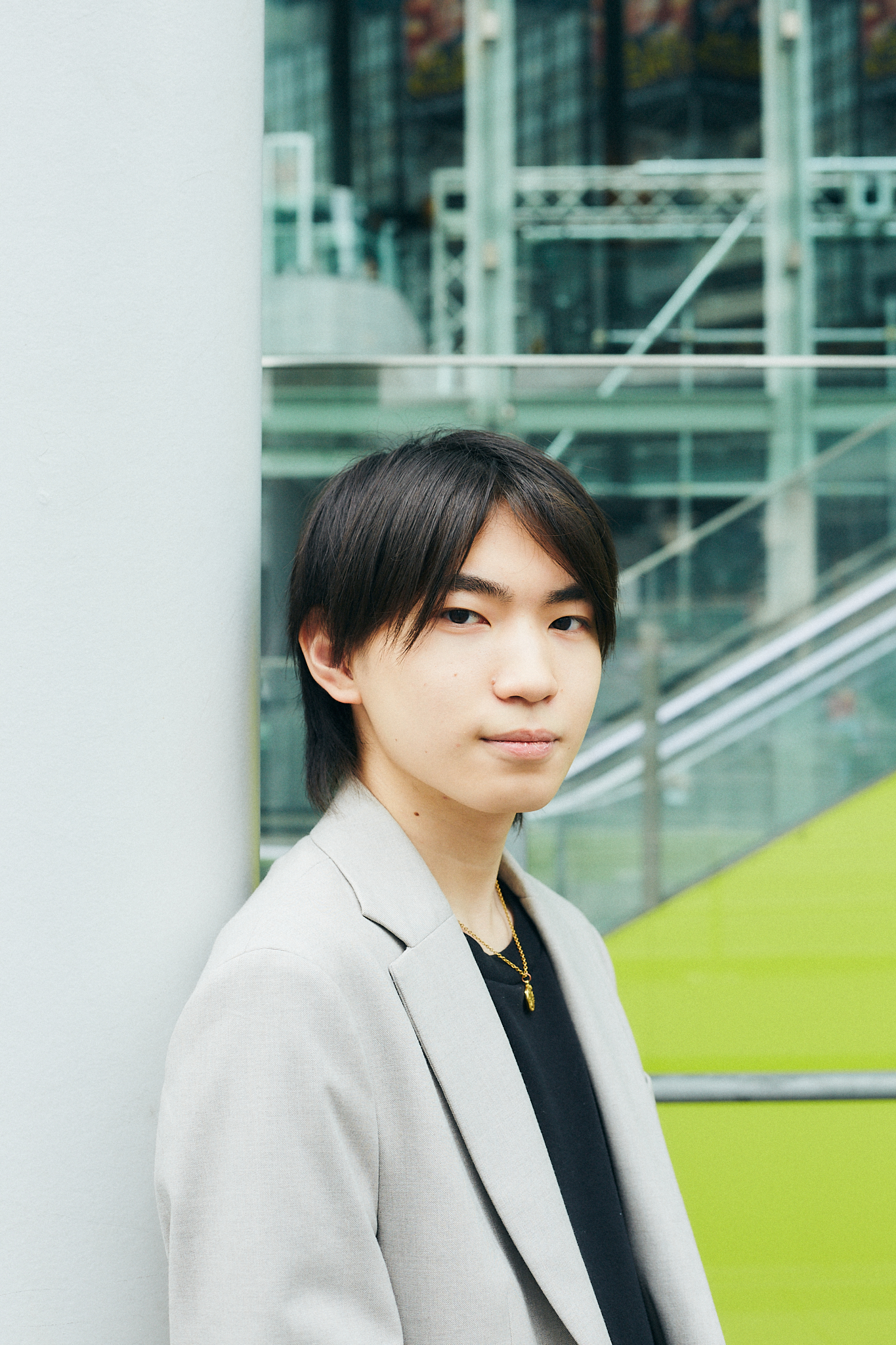
Q1.いま、力を入れていることは?
「高校の同好会で、全長5mものスペースバルーンを地球上空・成層圏にまで飛ばすプロジェクト『カイロスプログラム』を主宰しました。
プロジェクトの特徴は『想いプレート』というものをバルーンに取り付けたことです。これは、学校の生徒や協力企業のひとから日頃の気分、悩みについてつぶやきを募集し、ボードに表現したものです。つまりは、宇宙に自分の抱えている悩みや気持ちを飛ばしてしまうというものです。ほかにも、恵まれない子どもたちに給食が届く『おにぎりアクション』に宇宙を舞台に挑戦したりもしました。
いまは、宇宙のみならずAIに関心があって。2025年3月には、AIソリューションの開発や導入を行う企業『Artivation Corp.』を立ち上げました。簡単に言葉の定義を検索することができるアプリ『AI Dictionary』を筆頭に、さまざまなアプリを開発して、企業や学校に使ってもらおうと提案しているところです」
この投稿をInstagramで見る
Q2.活動を始めたきっかけは?
「小学生のころに通っていた小さな学習塾にて、AI時代を生き抜く術を肌で教わったことがきっかけです。
通っていた当時はAIという言葉すらメジャーではなくて。ですが、その塾の先生がAI時代を見据えた、”主体性を育む教育”をしてくれたんです。
印象に残っているのは、算数の問題を公式を習わずに解くように言われていたこと。正解の導き方を最初は知らないので、自分でロジックを考えて解法や公式をつくり出すところから始めます。その先生のもとでいつしかそれが自分の習慣になっていき、数学のテストで全国上位に入賞したこともあって。
こんな感じで、正解を導き出せるまでとことん考え続ける経験をしていたことは、いまの自分をかたちづくってくれていると思っています」

Q3.活動で大切にしていることは?
「壁をさらけ出し、頼る勇気を持つことです。
昔まで、少しだけ自信過剰なところがあり、ひとに助けを求めることを決してしない子どもでした。
ですが、スペースバルーンプロジェクトを進める上で、協賛金を企業からいただかなければならなくて。当初はどのようにプロジェクトの価値を伝えたらいいかわからず、プレゼンで5連敗したのですが、アドバイザーを筆頭にたくさんのひとに助けていただいて、突破口が開けたんです。
スペースバルーンを飛ばした経験は、愚直にやり続けていると、ひとの支えに出会えるのだと学ぶこともできて。自分の弱さや障壁をさらけ出し、頼ってみることは恥ずかしいことではなくて、真摯に向き合う気持ちを忘れずこそいればいいのだと、そこからは周囲のひとをいっそう大切にするようになりました」
Q4.活動を通して、実現したいビジョンは?
「自分の目標は、AIに面倒なことを任せ、人間はなにか生み出すことや探究することに専念できるような世界をつくることです。
会社の名前にもなっている言葉、Artivationは、『AIによる革新』という意味の造語になります。この会社の活動を通して『人類を真の知性文明にする』というゴールを目指しているんです。
その第一歩としていまやっているのが、AI Dictionaryをはじめとするプロダクト開発と導入支援です。AIが、空気や水と同じような社会インフラになるような未来を夢見ています」

Q5.将来の展望は?
「ヴィジョンについてと共通する部分があるのですが、まずは教育の力で 、一人ひとりの持つ『自分で考え動く力』 を芽吹かせたいです。
いまAIを使って開発しているアプリも、語学習得に活用できるものなので、これを通じて教育の領域に取り組み続けたいです。AIが当たり前にそばにある現代では、AIにはない人間の価値を発揮して仕事をしなければなりません。だからこそ、自分が高校生にして成層圏に手を伸ばすことができた体験をしたように、多くのひとに夢を自分の手で叶えて、好きなことを仕事にしてほしい。
だからまずは、AIの力を活用して、もっと多くのひとに夢を叶えられる実感を届けたいんです」

中田涼介のプロフィール
年齢:17歳
出身地:東京都大田区池上
所属:Artivation Corp.(Artivation株式会社) 芝国際中学校・高等学校 Space S同好会
趣味:ギター
特技:プレゼンテーション
大切にしている言葉:This is my life.
中田涼介のSNS
この投稿をInstagramで見る
Photo:Nanako Araie
Text:Taishi Murakami









Steenz_Breaking_News.png)
10代のリアル.png)

世の中.png)
特集.png)






