
世の中にあふれる情報から、10代が知っておくべき話題をお届けする「Steenz Breaking News」。今日は、タイの高校生たちが考えた「大気中の水分を飲料水に変えるシステム」についてご紹介します。
きれいな水を入手できない人が世界で20億人以上いる
日本では、蛇口をひねると簡単に得られる「水」。しかし、世界全体がそうとは限らないようです。公益財団法人 日本ユニセフ協会(以下、ユニセフ)は、世界には浄水処理された水を利用できない人々が2022年時点で22億人もいると発表しています。地球上に暮らす4人にひとりが水を安全に利用できない、という計算です。
水の管理がなされていない地域に暮らす人々の中には、湖や河川、野ざらしの井戸や用水路などを飲料水として使用している人もいるそうです。そうした浄水処理をしていない水には、多くの場合、菌や泥、動物の糞尿など、人体にとって危険な物質や不要な物質が含まれています。そのため、とくに抵抗力の弱い子どもが飲むと、下痢をおこし、最悪の場合は命を落とすケースも珍しくありません。

そうした事態を避けるためには、少しでもきれいな水を得なければなりません。しかし、サハラ以南のアフリカ諸国など生活用水が管理されていない地域では、そもそも水のある場所が限られているもの。場合によっては、何時間もかけて水を汲みに行く必要があります。水汲みは子どもたちの仕事になっていることも多く、重い水を運ぶだけで何時間も費やし、疲れ果ててしまうのだそう。その結果、学校に通えず、勉強する機会も奪われてしまうといった状況が、未だに根強く残っている地域もあるのです。
タイの高校生たちが、大気中の水分凝縮システムを開発
そんな中、14~16歳を対象とした「2024年ケンブリッジ科学コンテスト」において、安全な水の確保の一助となりうる技術が発表され、注目を集めています。コンテストの優勝チームである、タイの高校「アングロ・シンガポール・インターナショナルスクール」に通う4人が開発したのは、大気中の水分を集め飲料水に変える技術です。空気から水をただ集めるだけではなく、“安全に利用できる飲料水にする”ところがポイント。この技術が広がれば、水不足に苦しむ人々を助けられる可能性があります。

今回の優勝について、技術を開発した高校生たちは、「プロジェクトを通して、世界の水不足の規模の大きさを実感した」「わたしたちのプロジェクトは、すぐには問題解決につながらないかもしれない。けれど、チーム内の誰かが永続的な解決に貢献してくれることを期待している」といった内容を話しているそうです。
どのようなシステムなの?

では、大気中の水分凝縮システムとは、具体的にどのような仕組みのものなのでしょうか。
まず、冷却ポンプや冷却モジュールなどを利用し、装置内の温度を露点(※)に達するまで下げます。すると、冷やされた、空気中の水蒸気が、水滴に変化します。発生した水滴は、「集水器」と呼ばれる容器に溜められ、凝縮されます。なお、水の細菌汚染などを避けるために、このシステムでは、何層にもわたるろ過装置で空気の汚染を取り除くのだそうです。 そのため、システム内で発生させた水は、汚染物質の混入が低減した、安全な水となっています。
ケンブリッジ大学の発表によれば、今回のシステムで集めた水のpH値は7、つまり中性となっていたそうです。一般的に水道水のpH基準値は5.8〜8.6のため、それと同じ水準で空気中から水を生み出せるということになります。また、塩分濃度も低く、ミネラル含有量は蒸留水と同程度になるとのこと。
※露点:空気中に含まれる水蒸気が凝縮して結露し始める温度のこと。通常は15~20°C。
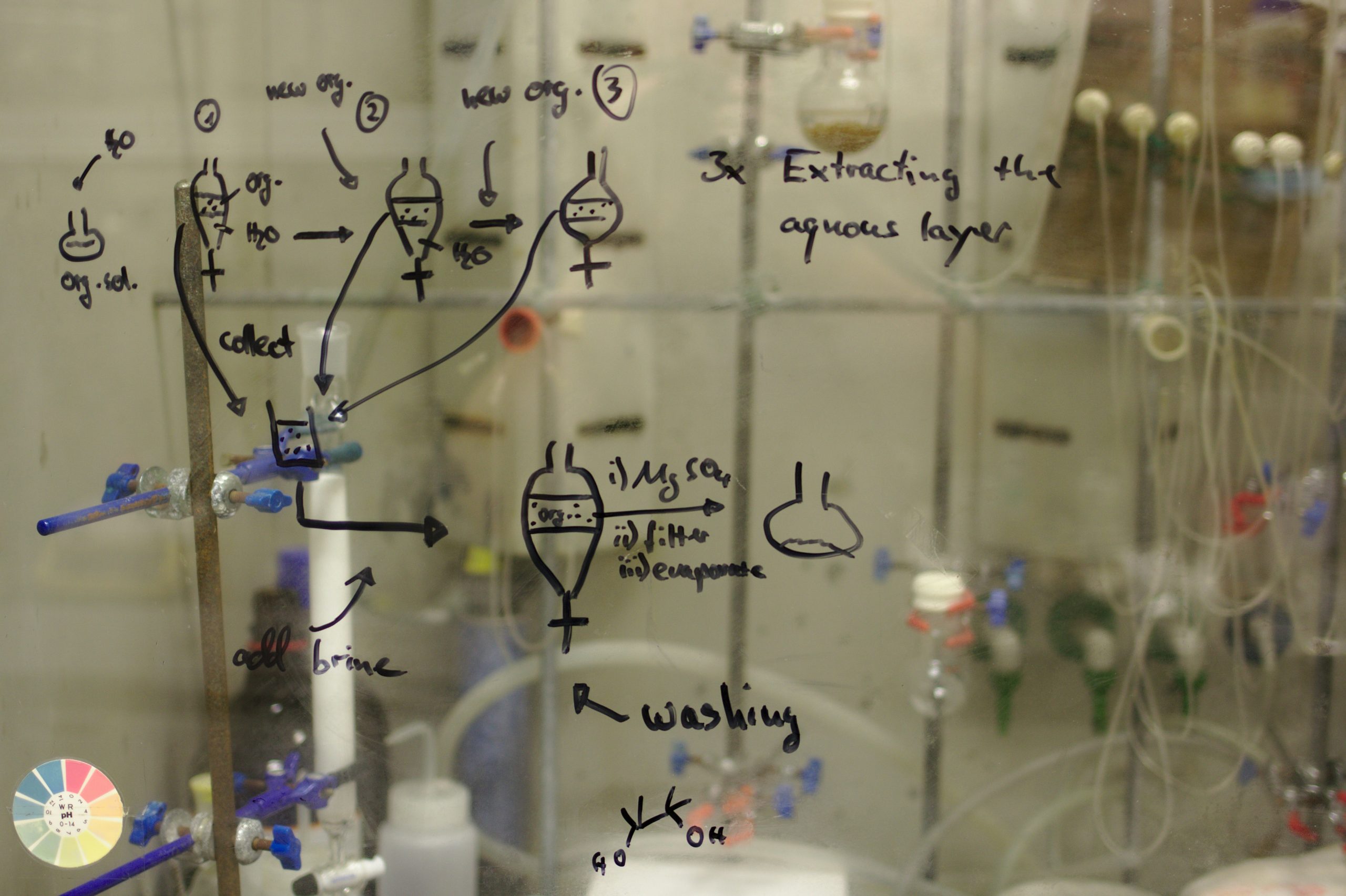
さらに、このシステムは初期のテスト時に、空気中に含まれる水蒸気の割合、いわゆる「相対湿度」が60%以上で、一日あたり最大50リットルの水を生成しました。湿度レベルが高いほど多くの飲料水を生み出せるということは、常に湿度が高い熱帯や亜熱帯地域で最も力を発揮するということです。これらの地域では、未だに水の衛生管理が行き届いていない場所が多いため、大気中の水を飲料水に変えるシステムは重宝されるのではないでしょうか。
水不足の解消はさまざま問題の解決につながるかも
世界の水不足問題を解決する手段として注目されている、大気中の水分凝縮システム。システムの実用化が進めば、不衛生な水を飲むことで命を落としたり、長時間の水汲みにより勉強する機会を奪われたりする子どもたちも減るでしょう。学ぶ機会を得られれば、それだけ就職先の選択肢も増え、貧困から抜け出せる可能性も高くなります。経済面が安定すれば、飢餓の問題も減るはずです。
このように水不足は、単に水が得られないというだけではなく、子どもの学習機会の損失や貧困、飢餓など、さまざま問題とつながっています。そういった背景も含めて、このシステムのような技術が発展することを願いたいですね。
Reference:
水道法第4条に基づく水質基準|厚生労働省
熱帯環境における水問題|藤田紘一郎著
Text:Yuki Tsuruda









Steenz_Breaking_News.png)
10代のリアル.png)

世の中.png)
特集.png)






