
世の中にあふれる情報から、10代が知っておくべき話題をお届けする「Steenz Breaking News」。今日は、微細藻類を活用したソリューション構築で、世界の環境問題や食糧問題などの解決に挑むスタートアップ企業「ガルデリア」についてご紹介します。
いま注目を集めるスタートアップ企業・ガルデリアとは?
2月28日、微細藻類(※)の研究開発を手がける株式会社ガルデリアが、総額4億円の資金調達を完了したというニュースが飛び込んできました。

同社は、主に温泉に生息する「Galdieria(ガルディエリア)」という微細藻類を扱い、環境問題や食糧問題、資源の循環利用(サーキュラーエコノミー)といった地球規模の社会課題の解決を目指すスタートアップ企業です。2015年に現CEOの谷本肇さんらによって設立されました。
※微細藻類:藻類のうち、1mm~1㎛ほどの大きさの、淡水・海水・堆積物などの水分中にみられる植物プランクトンのこと。
ユニークな特性を持つ藻類「ガルディエリア」とは?
ガルデリアが扱う「ガルディエリア」という藻類は、一般的な藻とは大きく異なる性質を持っています。温泉などの高温・高酸性な場所や、CO2濃度の高い場所、硫黄酸化物や窒素酸化物が存在している場所など、一般的な生物が生存できないような過酷な環境でも生育が可能です。光があれば光合成をしますが、光がない暗い場所でも、栄養があれば生きていくことができます。
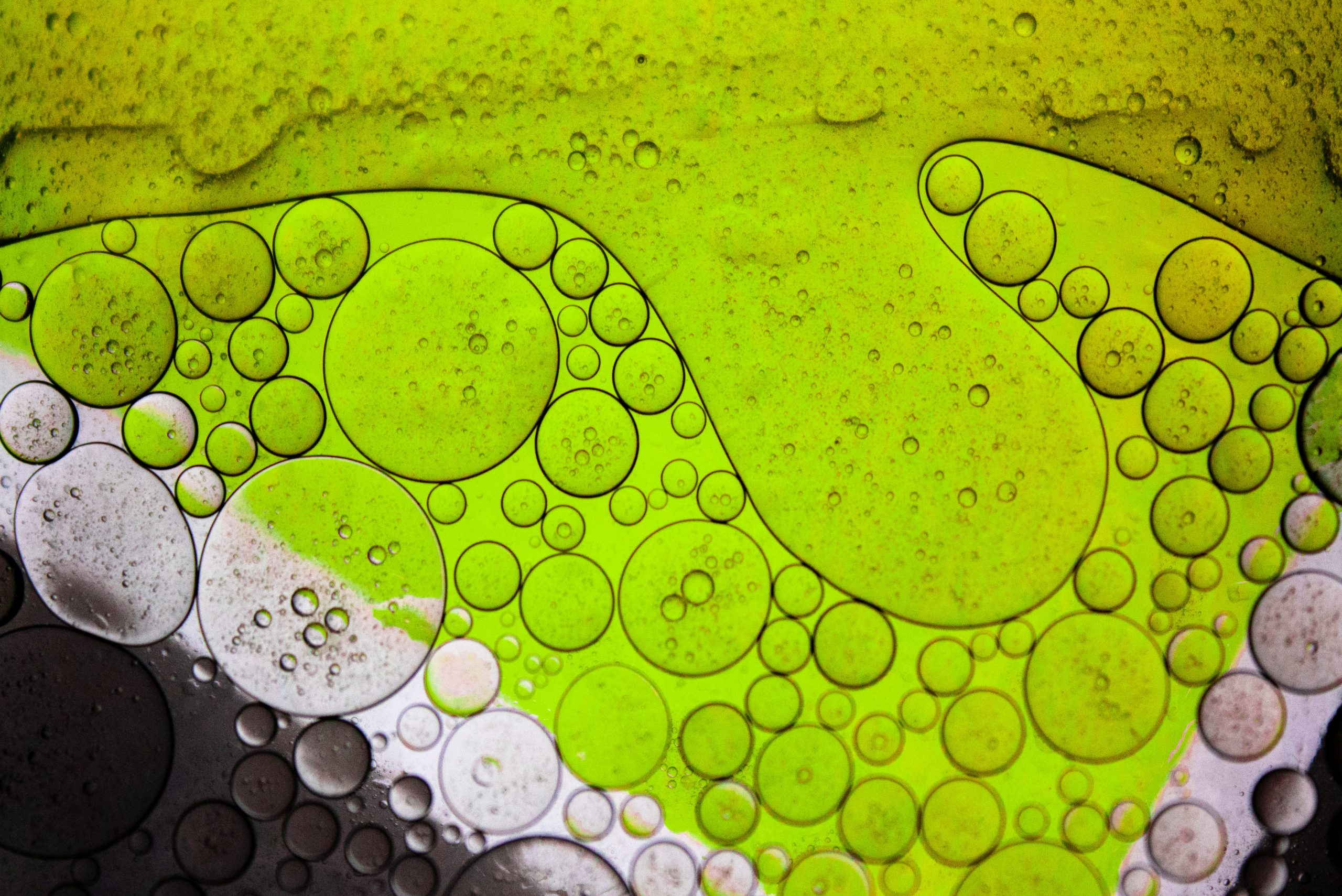
「ガルディエリア」には、さらに特殊な能力があります。金(Au)やパラジウムといった金属が含まれた水溶液から、金属だけを選び分け、細胞の表面に吸着させることができます。
ガルデリアは、こうした特性を活かすことで、現代社会が抱える地球温暖化や都市鉱山などの問題解決に結び付けようとしているのです。
ガルデリアが解決を目指す3つの社会問題
ガルデリアが解決を目指す社会問題は、大きく3つあります。
① 都市鉱山の問題
1つ目が、都市鉱山の問題です。私たちが捨てる家電製品などには、実はとても価値の高い金属が含まれています。これらを「都市鉱山」と呼び、それらの中からまだ利用できる金属資源をリサイクルすることに、昨今高い注目が集まっています。

ガルデリアが開発した吸着剤は、藻類の「ガルディエリア」の特性を活かしたことで、特に金(Au)とパラジウムのリサイクルにおいて、これまで捨てられていた低濃度の溶液からも金属を回収することが可能となりました。
さらに、複雑な混合物からでも特定の金属だけを選んで吸着でき、例えば金属の「すず」が多く含まれる溶液からパラジウムだけを取り出すような高度な分離も実現可能です。
こうした技術により、これまで捨てられていた貴金属を回収することで、鉱山から新たに金属を掘り出す必要性が減り、環境への負荷低減を図れます。また、現在の貴金属回収には石油由来の化学物質が使われていますが、ガルディエリアを活かした吸着剤を使うことでCO2排出量の削減にも貢献できます。
②天然金鉱山における環境汚染
世界の金採掘市場では、人の手によって小規模な金(Au)の採掘をおこなうことが大きな問題となっています。この問題は世界70カ国に広がっていると言われ、小規模な金(Au)の採掘は世界の金産出量の約2割を占めているとされており、深刻な環境問題と社会問題を引き起こしています。

小規模な金(Au)の採掘現場では、人体に有害な水銀を大量に使用しています。その結果、環境汚染が発生。採掘現場で働く人を含め、周辺に暮らす人々の健康に悪影響を及ぼしています。
ガルデリアは、この問題に対して、有害物質を全く使わずに金(Au)を回収できる方法を開発。日本で特許も取得しています。従来の方法よりも多くの金(Au)を採取できるため、環境に配慮しつつ経済的にもメリットがある技術を提供しているのです。
③サーキュラーエコノミーの促進とCO2削減の問題
私たちの社会は現在、地球から資源を取り出して使い、捨てるという一方通行の仕組みになっています。ガルデリアは、この状況を変えるべく、「ガルディエリア」を活用しようとしています。
「ガルディエリア」は、光とCO2があれば育ちます。特に工場の排ガスに含まれる高濃度のCO2を吸わせて培養することができるため、環境への負荷を減らしながら育てることが可能です。

さらに、「ガルディエリア」は藻の一種のため、細胞表面をCO2や貴金属の吸着に使った後は、そのほかの成分を魚の餌や人間の食料、農業用肥料として活用できる可能性を秘めています。これによって、資源を循環させる社会の実現に貢献することが期待されています。
自然界の力に改めて目を向ける
温暖化、資源枯渇、食糧問題……。さまざまな問題に直面する私たちですが、ガルデリアの取り組みから、小さな藻類の力が複数の社会問題を同時に解決できる可能性に驚かされました。最先端テクノロジーだけでなく、自然界の力も活用する視点を持つことが、持続可能な社会への新たな道筋になるのかもしれません。
Text:Teruko Ichioka









Steenz_Breaking_News.png)
10代のリアル.png)

世の中.png)
特集.png)






