
21歳、東京の郊外でぽけ〜っと暮らす、音楽ナードの渡辺青が日々のDIGりの中で出会ったさまざまな「これ聴いて!」な音楽たちを、新旧問わずに紹介していく企画「渡辺青のこれ聴いて!」
今回紹介するのは、2021年のデビュー以降注目され続けるUKを拠点とするアーティスト、Nala Sinephro(ナラ・シネフロ)。没入感の高い唯一無二のヒーリングサウンドはハマるとなかなか抜け出せません。私も最近ループしまくってます。
昨年には来日公演も果たした彼女、知らないなんてもったいない!
変化しながら繰り返す
瞑想的と評されるサウンド、無重力空間に飛ばされたかのような感覚。『Endlessness』「終わりのない」(日本盤の帯には「終わりのない世界」と訳されている)と名付けられたこのアルバムは、カリブ系ベルギー人ミュージシャン、ナラ・シネフロの21年デビュー作以降3年振りに発表された彼女のセカンド・スタジオアルバムだ。

全10曲、それぞれContinuum(連続体)○○とナンバリングされた曲たちは、彼女の扱うモジュラーシンセサイザーから流れるアルペジオが軸となり、「輪廻」というテーマのもと、サックス、ドラム、バイオリン、ハープ、ピアノなど様々な楽器の演奏と共に繰り返しながら変化していく様が描かれる。
生音と電子音の境目が見えにくい程に音と音を溶け合わせたサウンド作りと、繰り返され続けるそのアルペジオに、自分が今、どこにいるのかよくわからなくなってくるような感覚は恍惚的で美しく、ずっと身を委ねていたくなる。
このアルバムを再生すると、いつも気がついたら終わっていて、驚く。
それほどに曲と曲の境目がなく、わかりにくい。輪廻や連続体というワードから、それが意識的に作られていることがわかる。前作の『Space 1.8』では、1曲をひとつの場所、つまりスペースととらえて制作していたという彼女だが、今作ではそれが45分間のアルバム一枚の中で表現されているように思う。
フィッシュマンズの『Long Season』とかを想像してもらえるとわかりやすいかも知れない。
変化しながら繰り返す。それは微細なものであったり、時にものすごい高まりを感じるものであったりする。これを作るのってめっちゃ根気だよなあ〜と純粋にビビるのと同時に、逆になぜ1曲の区切りをつけているんだろう、曲順はどうやって考えたんだろう?みたいな。わかりにくいからこそ考えることが沢山あって楽しい。
これってなんて音楽だ?

聴き込んでいくほど、このアルバムや彼女の持つ音楽性の表現に悩んでしまう。参加しているアーティストはジャズアーティスト達で、(1曲だけポストパンクバンドBlack Midiのドラマー、モーガン・シンプソンが参加している。)その幽玄な世界観はアンビエントと言われているものに当たるだろうし、リラクシングなサウンド感やモジュラーシンセの使われ方はニューエイジっぽさを感じさせる。
結局「アンビエント・ジャズ」と括ってしまうのが一番簡単に思えるのだけど、彼女は話題になった前作、『Space 1.8』を完成させるまで、アンビエントミュージックが一体何なのかすら知らなかったというので驚く。
彼女は自らのことを「コンポーザー」と称する。むしろ、「ジャズアーティスト」とか「女性ハーピスト」(彼女はモジュラーシンセの他にペダルハープも演奏する。)とか呼ばれるのは勘弁してくれとでも言いたげだ。
ナラ・シネフロは1996年、ベルギー、ブリュッセル生まれ。 森の近くに住む音楽好きな一家のもとに育ち、小さい頃からとにかく楽器に触れてきたという。
彼女の初期のキャリアは未だ謎が多いが、名門ジャズ大学をドロップアウトした後、10代後半でロンドンに移住。新世代UKジャズと言われるジャズアーティスト達とのコミュニティと出会い、レコード屋で働きながら2018年8月からファーストアルバム『Space 1.8』の制作を始め、2021年に名門レーベルWarpから発表する。同年、アルバムリリースの直前には、彼女が一時期レジデントDJを務めていたNTS Radioのレーベルから16分のライブ音源を発表している。こちらはかなりアグレッシヴな内容。
ナラ・シネフロと新世代UKジャズ

『Endlessness』では、今年フジロックにも出演する現行UKシーンを代表するバンド、Ezra Collectiveのジェイムズ・モリスンや、アーバン・アフロ・ジャズバンド、kokorokoのシーラ・モーリスグレイにソロ・サクソフォニストのヌバイア・ガルシアなど、音楽好きには聞き覚えのある面子が揃っている。同時に、彼らは新世代UKジャズを代表するアーティスト達だ。
そもそも新世代UKジャズってなんなのよ?というところだが、2018年のコンピレーションアルバム『We Out Here』を皮切りに注目を集めた、UKの現行ジャズシーンのアーティスト群というのが良いかもしれない。
前述のEzra Collectiveを筆頭に、オーセンティックなジャズではない特有のシーンを築いていて、アフロビートやUKガラージなど、UKのダンスミュージックカルチャーや独自のヒップホップ文化に触れて育ってきた世代ということも特徴だ。
前作『Space 1.8』でも同様、ナラ・シネフロの作品にはその界隈のアーティストが集まっている。それは彼女の作品に限ったことではなく、新世代UKジャズの横のつながりの強さを表しているような感じで、彼らのアルバムのクレジットやライブ映像を見ていくと、リスナー目線でもそれが良くわかる。
ここら辺のアーティストは実はみんな同じカルチャースクール出身で……などなど、深掘っていくと本当に面白い。興味のある人は、音楽批評家、柳樂光隆氏監修のUKジャズ・シーン相関図を見てみてほしい。マップの中心となっている、2020年発表のブルーノートの名曲が現行アーティスト達によって再解釈されたアルバム、Blue Note Re:imaginedや、サウスロンドンのコレクティブ&レーベル、Touching Bassのコンピ(ナラ・シネフロも参加)も手掛かりとして有効だ。
何にも囚われようとしない彼女の音楽
ナラ・シネフロの多くはないインタビューでの発言から、有色人種であること、女性であることへの差別や色眼鏡に対して静かな抵抗をずっとしてきたこと、そして、もうそんなのにはうんざりだ!と感じているような様子がうかがえる。

アリス・コルトレーン、ドロシー・アシュビー、最近ではブランディー・ヤンガーなど、なぜか著名なジャズハーピストは女性が多く、ステレオタイプ的な見られ方に辟易していることもあるだろう。自らの音楽性を定義されることに対する窮屈さも彼女はそこで語っていた。
現状、Ezra Collectiveはグライムをジャズにはめ込んだ曲を出していたり、ヌバイア・ガルシアはリミックスアルバムを発表していたり、UKジャズのシーン全体にジャンルをぶち抜こうとする空気感があるのは確かで、その土壌があるからこそ彼女の音楽は生まれ、聴かれているのかもしれない。その自由さはとても魅力的だ。
私は音楽が大好きだが、色んなことを知ろうとしていくと、その山頂の高さにクラっとくる時がある。そんな時は彼女のアルバムを聴きたい。いい、悪いとか、凄い、凄くないとかじゃない。
何にも囚われようとしない彼女の音楽を聴きたいのだ。
購入:
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=14242
出典:
https://rollingstonejapan.com/articles/detail/37041/2/1/1#google_vignette
https://pitchfork.com/features/rising/nala-sinephro-interview/
Edit: Himari Amakata
Writer: 渡辺青



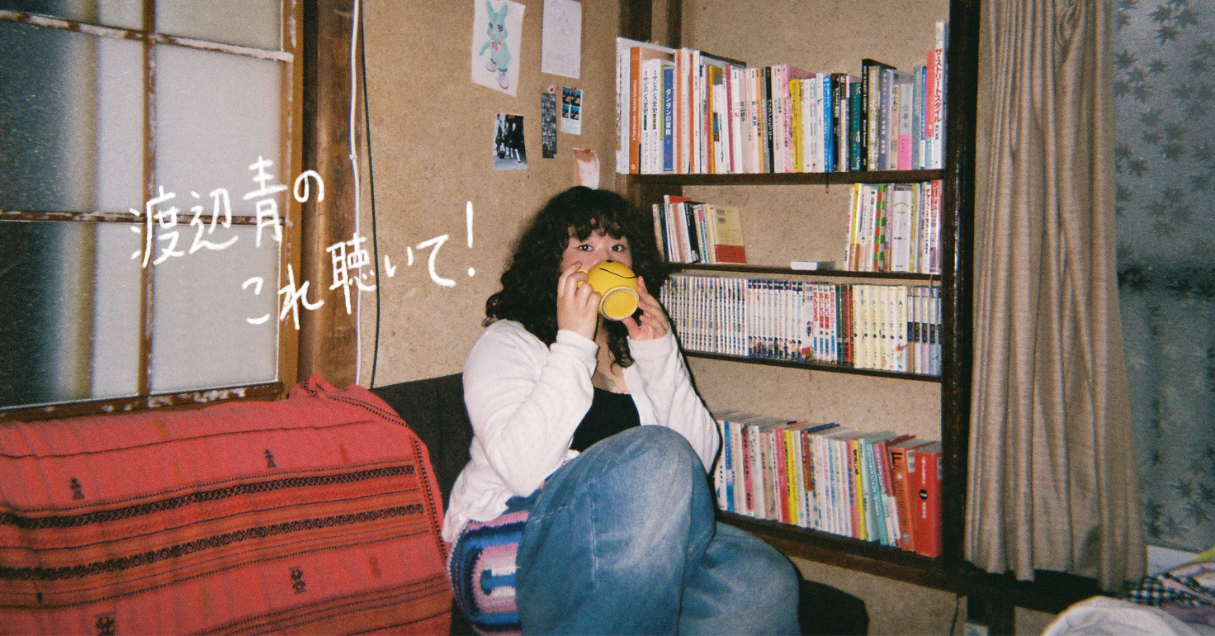




Steenz_Breaking_News.png)
10代のリアル.png)

世の中.png)
特集.png)






