
世の中にあふれる情報から、10代が知っておくべき話題をお届けする「Steenz Breaking News」。今日は、NFTを活用した農業をソーシャルグッドにする取り組みについてご紹介します。
さまざまな場所で活用されているNFT

NFT(ノンファンジブルトークン/Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン技術を用いてつくられる、代替不可能な唯一無二のデジタルデータのことです。
通常のデジタルデータは複製が可能ですが、NFTはブロックチェーン技術によって固有の識別子や所有者情報が与えられ、データの改ざんができないとされています。そのため、ひとつひとつのデータに希少性が生じ、資産価値が生まれ、所有権などもデータに反映させられることから、マーケットでNFTの売買が成立しています。
NFTは現在、デジタルアートや音楽、ゲームアイテム、仮想空間上の土地など、さまざまなものに使われています。

世界のNFT市場は、2022年時点で約30億5,600万米ドルの規模があります。この市場規模は、2027年までには136億7,900万米ドルとおよそ4.5倍に成長すると予測されており、世界と比較するとNFTの認知率・保有率ともに未だ低い日本市場においても、その将来性が注目されています。
そんなNFTですが、環境保護や地方創生などの文脈で活用されるケースもあり、企業や自治体などが今後の可能性を模索しはじめています。
農業分野にNFTを活用する事例も
より良い社会を目指すための方法のひとつとして活用され始めているNFT。今回は、その中でも農業分野でのNFT活用事例について見ていきましょう。
ひとつめにご紹介する事例は、Metagri研究所の「選べる柑橘接ぎ木NFT オーナーシップ」です。
このプロジェクトでは、シークワーサーに希少な柑橘新品種「あすみ」や「あすき」を接ぎ木(植物の茎や枝などの一部を、他の植物の枝や茎などとつなぎ合わせること)し、自分だけのオリジナル柑橘を育て、収穫することを目指します。

2025年2月に発表された同プロジェクトでは、1本あたり 10万円(税抜)で限定3本の接ぎ木参加権が発売されました。購入者はNFTで発行されたオーナー権を持ち、2027年4月頃の収穫時期に自分が所有する枝から収穫されたオリジナルの柑橘を味わうことができるそうです。
果物の種を減らすことや、病害に強くすることなどを目的に行われる品種改良の方法のひとつである接ぎ木。NFTとのかけ合わせが興味深い取り組みです。
「規格外りんご×NFT」で購入者に新たな価値を届ける取り組み

次は、色や形が不ぞろいなどの理由から、一般市場に出回ることのない規格外農作物にスポットを当てた取り組みをご紹介します。
福島県国見町の未利用資源を生かした事業展開などをおこなう株式会社陽と人が、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社とともに手がけるプロジェクト『farm to table』です。
同プロジェクトでは、農業の「生産~配送」という一連の流れの中でどうしても発生してしまう環境負荷の軽減や、生産者と消費者の新たな関係性構築を目指しています。
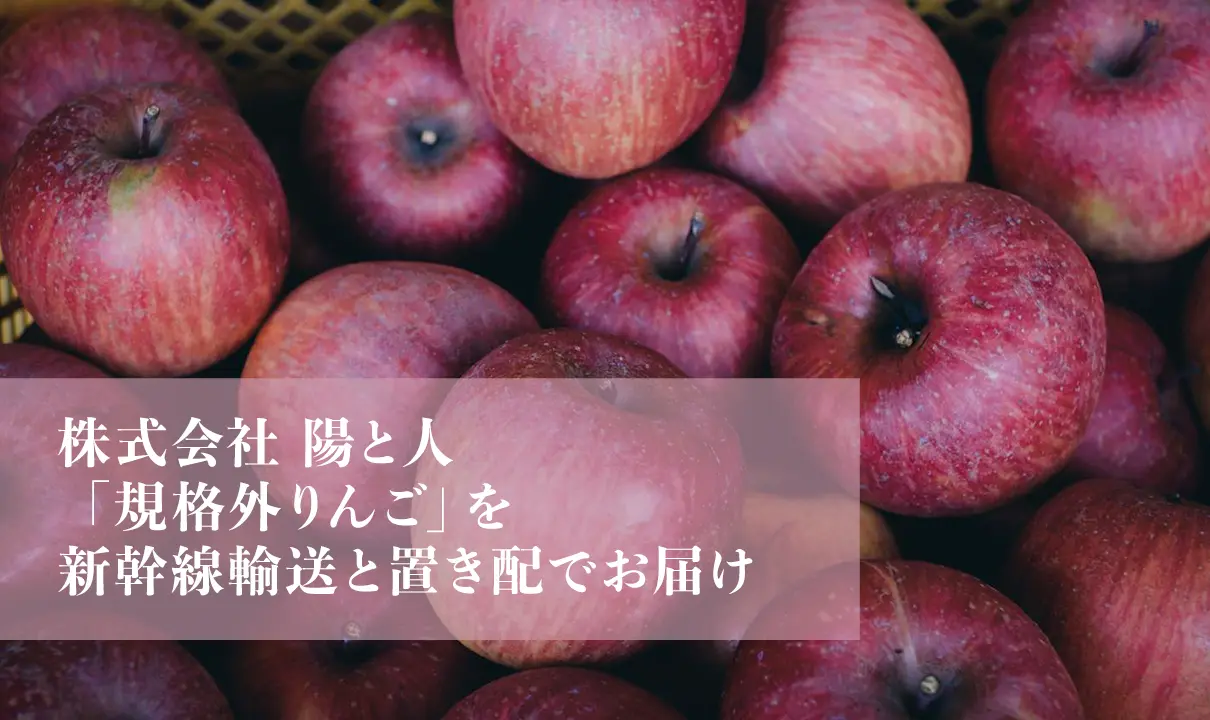
具体的には、福島県産の「規格外りんご」を郵便局の『ふるさと小包』というサービスで取り扱い、購入者のもとに商品を届ける際、新幹線を利用した輸送や置き配をおこないます。これにより、食品廃棄量の削減、配達時のエネルギー効率の向上、再配達の削減を目指すのです。
また、規格外りんごが届くだけでなく、NFT特典も同梱されるそう。これにより、生産者・生産地と消費者間の情報発信やコミュニケーションや新しい関係が生まれるのか、今後の動向にも注目です!
SDGsにも貢献できる!NFTの可能性に期待
NFTと聞くと、デジタルアートなど、デジタルの世界での取引を思い浮かべてしまいやすいもの。ですが、今回「農業×NFT」の取り組みを見てきたことで、NFTにはもっと幅広い可能性があるように感じました。
NFT市場の今後の可能性に注目しつつ、NFTが社会をより良くするきっかけとなっていくことを期待したいと思います。
Reference:
【申し込み】選べる柑橘接ぎ木NFT オーナーシップ – Metagri研究所
Text:kagari









Steenz_Breaking_News.png)
10代のリアル.png)

世の中.png)
特集.png)






