
hi, it’s kanon ; )
スペイン留学もいよいよ終盤に差しかかってきました! 交換留学生ということで、今回は留学の本目的である勉強について! スペインの大学の試験の特徴や、私がどのように勉強してきたかについて紹介します。
日本とは違う学びのスタイル
私が1年間通ったバルセロナの大学「ESADE」では、授業スタイルがとても多様でした。たとえば、外交問題や領事館に関するプレゼンを毎週行い、その積み重ねが成績に反映される授業もあれば、授業中の発言や態度なども一切関係なく、期末試験だけで成績が決まる授業もありました。そのため、授業ごとに予習・復習の方法を工夫し、勉強スタイルを自分なりに柔軟に変えて対応する必要がありました。
日本でわたしが通っている大学と大きく違うと感じたのは、「予習」の重要性です。ほぼすべての授業で何かしらの資料を読んでから授業に臨むのが前提になっていて、授業の最初にその内容についてディスカッションが始まることもしばしば。なので、家での事前準備は欠かせませんでした。
試験の特徴いろいろ
期末試験の方法もさまざま。たとえば、「Real Estate Transaction Law(不動産取引法)」の試験では、実際の取引を元にしたケーススタディが出題されたり、「Geoeconomics(地経学)」の試験では事前に20問の出題候補が配られ、その中から5問がランダムで出題される形式。事前にインプットしておいた答案を3時間ひたすらペンを走らせて回答するスタイルでした。

一番「楽だった」と感じたのは、30問の選択式テスト。楽と言っても、不正解だった場合、その問題の「得点が得られない」のではなく、「減点」されてしまうというシステムなので、知識があいまいなままでは太刀打ちできません。一度だけ、日本でも減点方式の試験を受けたことがありましたが、スペインではこれが当たり前というのにも驚きました。
中間・期末試験に向けた勉強法
わたしはもともと詰め込むタイプで、日本では、試験の2日前くらいから勉強し始めてなんとかなってきました。でも、スペインではそれがあまり通用しない……!
試験範囲が広いこともあり、それぞれの試験の1週間前からは本腰を入れて勉強するように。部屋を掃除してからでないと、きちんと集中することができないので、まずは部屋を掃除(笑)。その後、ジャズのプレイリストを流して“勉強モード”に入ります。
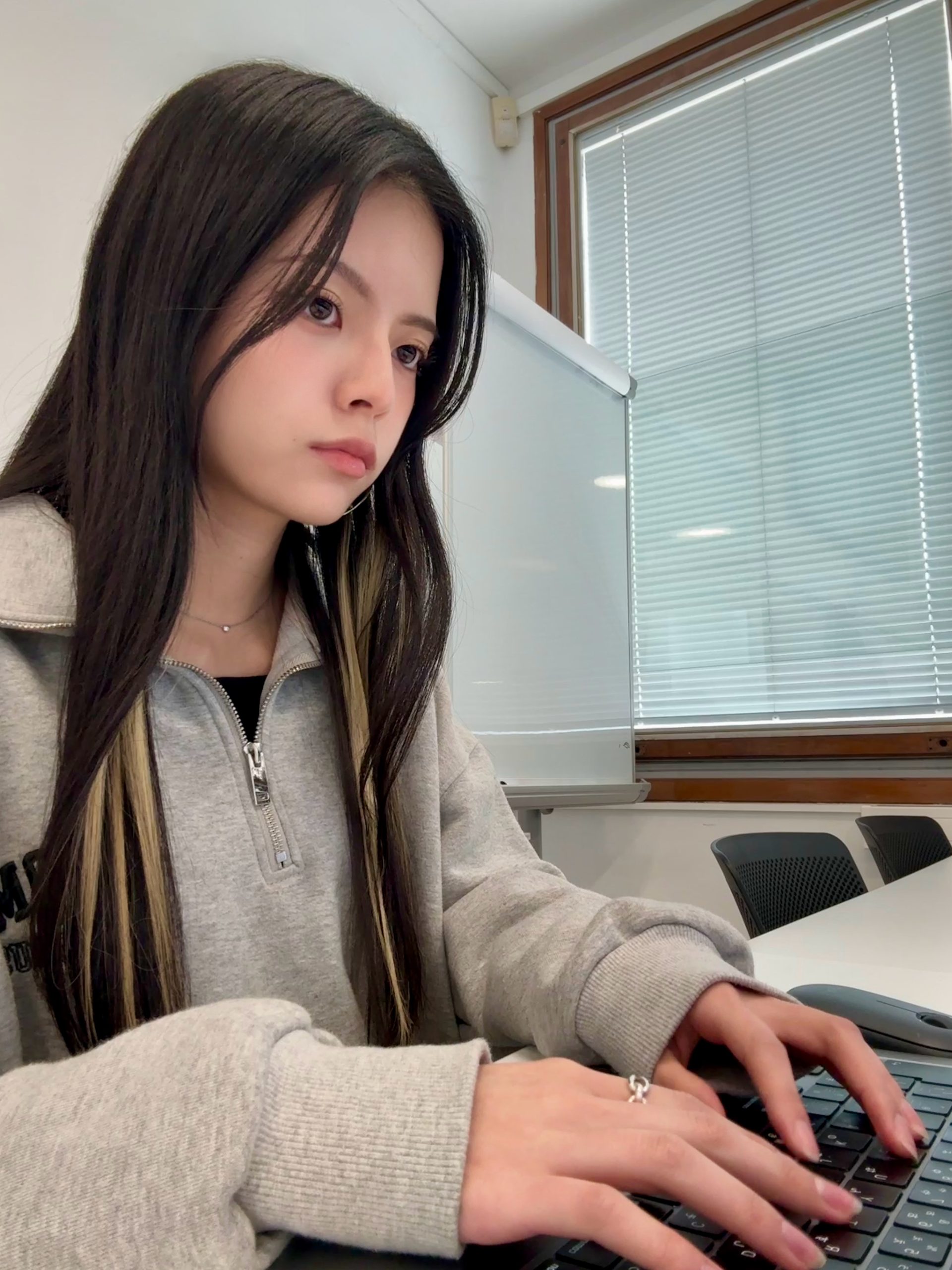
勉強法はとてもシンプルです。
- 授業のスライドと自分のノートを照らし合わせながら「study guide」を作成
- それをiPadに転送し、4色でハイライトして覚えていく
- さらに重要なポイントは手書きで整理
- 最後はノートを見ずに、覚えていることをひたすら書き出して確認
このやり方は高校時代から変わっていないのですが、最近はAIも活用! ノートの内容を読み込ませて、問題集を作ってもらったりと、勉強範囲が広い分、スペインに来てからは勉強の効率化にも力を入れています。
レポートの“ボリューム感”
もうひとつ驚いたのが、レポートのボリュームです。英文で10〜15ページは当たり前!
たとえば、「European Law of the Financial Markets(欧州金融市場法)」の授業では、PRIIPs規制という、個人投資家向けの金融商品に関する規制における契約前開示について3,000字の分析レポートを書かなければなりませんでした。
日本でも、5,000字のレポートが課される授業はありますが、それは一部の授業だけ。スペインでは、3,000字クラスのレポートが頻繁に出されるので、かなり書く力が鍛えられました。
レジデンスでの勉強環境
わたしが住んでいるのは学生用レジデンス。日本の学生会館に近いもので、さまざまな大学・大学院の学生が暮らしています。そのため、自習室やグループワーク用のスペースなども充実しています。
スペインの学生も試験期間中は大学の図書館にこもる人が多いですが、わたしは空きコマのとき以外は、ほとんど自宅で勉強していました。集中が切れたときや、友達と一緒に勉強したいときには、レジデンスの自習室がちょうど良い場所でした。

スペインでの学生生活は、日本とは違うことだらけ。でも、学ぶ内容はどれも刺激的でおもしろく、これまでのスタイルにこだわらず、柔軟に対応する力が身についたのは大きな収穫でした!
kanonのプロフィール
東京都出身。スペインに留学中の大学4年生で、モデルとしても活動。
Steenzの運営メンバーで、ポッドキャスト「Seriously Kidding」のMCも務めていた。









Steenz_Breaking_News.png)
10代のリアル.png)

世の中.png)
特集.png)






