
「気になる10代名鑑」の1094人目は小松和滉さん(17)。オジギソウが持つ「記憶の機能」に興味を持ち、複数の団体に所属しながら研究を進めています。その傍ら、地方の地域格差についても考えるようになったという小松さんに、そのきっかけや、研究者としての今後の展望まで、詳しく聞いてみました。
小松和滉を知る5つの質問
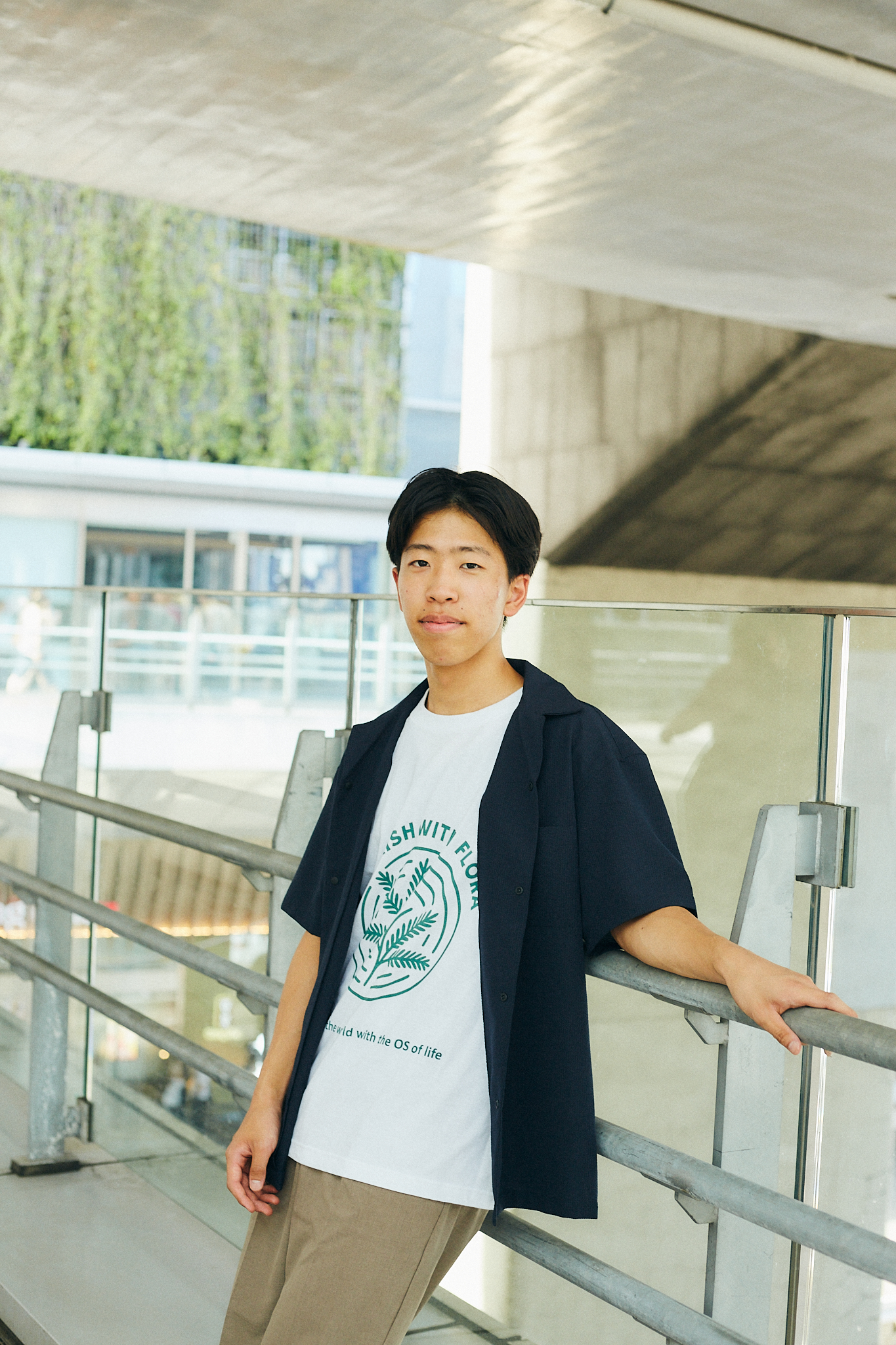
Q1.いま、いちばん力を入れている活動は?
「オジギソウの研究と、その研究を活かした教育普及活動に力を入れています。
オジギソウという名前は多くの人が耳にしたことがあると思うのですが、実は『記憶』の仕組みを持っている植物でもあるんです。そこに魅せられて、日々研究をおこなっていて。
地元の長野を拠点にしていますが、N高校研究部や東京大学の科学プログラムのUTokyoGSC-NEXTなど、複数の研究団体に所属をしているため、研究手法も、ともに研究している人たちの年齢や立場も幅広いです。
また、この研究経験を活かし、友人といっしょに地方の子どもたちが科学に触れる機会を増やすことを目的とした科学教室も企画・運営しています」
塩尻市内の小学校にて、科学実験教室を実施してきました!!
12月に続いて2回目の実験教室となります。
近頃、季節外れの桜も咲いているということで、今回の実験教室では「化学の花を咲かせよう」と題して、尿素の結晶づくりの実験を行いました。
めちゃくちゃ楽しかったぁ! pic.twitter.com/JvFTrX9Uia— Kazuhiro Komatsu | 小松和滉 (@kazu_koma08) January 27, 2025
Q2.活動を始めたきっかけは?
「最初にひとつの植物に興味を持ったのは5歳のころです。
幼少期からずっと長野で暮らしていて、自然や生き物はごく当たり前の存在でした。ただあるとき、ネムノキの葉が夜に閉じる姿をみて、まるで眠っているようで不思議に思って。この幼少期の純粋な疑問が、中学1年生からのオジギソウの研究へつながったと思います。
教育普及活動の原点は、研究をおこなっていて感じた、研究アクセスの地域格差にあります。実際、中学2年生のとき、自分が行った実験の発表を東京でする機会があったのですが、都市部の同級生が大学で使うような専門装置を使っているのを目の当たりにして、とても驚いて。
もちろん、長野での研究はメリットもあって、実際に研究対象の植物に触れられるというのは都市部ではなかなか難しいのではないいんじゃないかなって。触れあってこそわかるものもあると思いますし……。
だからこそ、都市部でも地方でも、場所を問わず誰もが科学の探究を楽しめる環境をつくりたいと強く感じて、友人たちと科学教室をはじめました」

Q3.活動をしている中で、印象的だった出会いは?
「自分の研究の分野を見てくれている教授との出会いです。
自分が所属しているN高校研究部、UTokyoGSC-NEXTでは大学の先生と繋げてくれるシステムがあるんです。自分の研究を専門家の視点から見てもらうと、考察が一気に深まり、新しい研究の道が開けることがとても嬉しくて。
だから、所属団体以外にも、能動的に自分でプログラムを探すようにしていて。はじめて学会に参加したときも、知らない人とでも積極的に意見交換をする先輩の姿に衝撃を受けて。機会は自分で取りにいかないといけないんだと学びましたね。
あとは、 科学教室で子供たちが目を輝かせながら実験に取り組む姿も、活動を続ける大きな原動力になっています」
Q4.活動するうえで、大切にしていることは?
「『Fail First(まず失敗せよ)』という言葉が自分の行動指針です。
この言葉は、 中学生の頃、長野で参加したリーダーシップ研修で出会って。ここで学んだ言葉遣いや立ち振る舞いはもちろんですが、『Fail First』のおかげで、結果を恐れずに新しい研究手法や未開拓のテーマに挑戦し続けることができています。
また、自分の研究メンターである先生からは、科学的な探究の姿勢にくわえて、研究者としての心構えも学んでいて、そこで教えていただいたことは常に意識をしています。
心構えと言ってもさまざまで、ノートをきちんと取るだとか、不正をしてはいけないなど、基本的なところからはじまって、研究者とはどういう存在なのか、社会にどう貢献していくのか、など答えの出ないようなものまであります。
そういったことを含めて、ただ知識として自分のなかに貯めるのではなく、教えてもらったことを自分なりに咀嚼し、考えることも大切にしています」
Q5.将来の展望は?
「『人間と植物が共生する社会』を実現したいと思っています。
生活の中で身近にある植物は、“雑草”とひとつの言葉でくくられてしまいますが、その植物の一つひとつにも名前と個性があって、必ず面白い能力を秘めているんです。人間と植物が助け合い、植物のポテンシャルを十分に引き出すことができれば、農業や環境問題をはじめとする、あらゆる問題の解決につながるのではないかと思っています。
それぞれの植物の価値が認識され、尊重される世界のために、まずはオジギソウ研究を通じて植物への見方を変える契機をつくり、人間と植物との新たな関係性を社会に提案することを目標にしています。
加えて、かつての自分が感じたような研究環境の地域格差をなくし、探究心をもっていれば研究に挑戦できるような社会基盤を作ることも大きな目標です」
小松和滉のプロフィール
年齢:17歳
出身地:長野県岡谷市
所属:長野県諏訪清陵高等学校、 N高校研究部、UTokyoGSC-NEXT、ADvance Lab
趣味:スキー、スノーボード、ハイキング
大切にしている言葉:Flourish with Flora
小松和滉のSNS
★X
サイエンスキャッスル関東大会2024に出場してきました。脳をフル稼働させてディスカッションをし、最高の一日になりました!
同世代の中高生の高度な研究から刺激を受けるとともに、たくさんのつながりを作ることができた有意義な時間でした。この熱量と出会いを大切に研究を進めていきます! pic.twitter.com/73Gwt7O0NH— Kazuhiro Komatsu | 小松和滉 (@kazu_koma08) December 7, 2024
Photo:Nanako Araie
Text:Manami Tanaka









Steenz_Breaking_News.png)
10代のリアル.png)

世の中.png)
特集.png)






